ステッピングモーターはステップ角(位相数など)、静トルク及び電流の3つの主な要素から構成されています。この3つの主な要素が決定されたら、どの型番にするかも明確になるでしょう。
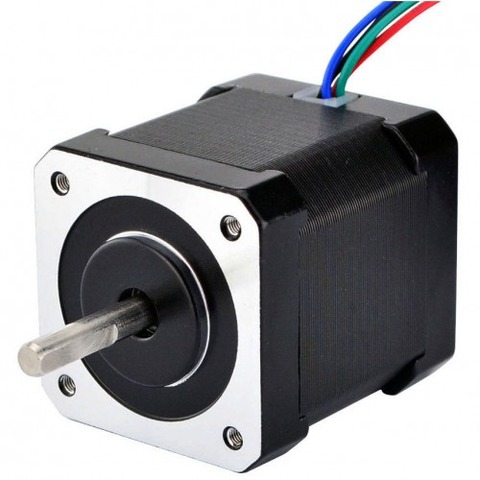
1、ステップ角について
ステッピングモーターのステップ角は負荷領域の精度によります。モータシャフト上、負荷の最小分解能(当量)を各モーター当量(減速を含む)の角度に変換します。 モーターのステップ角はこの角度以下でなければなりません。 現在市場では、ステッピングモータのステップ角は、一般に0.36°/0.72°(5相モータ)、0.9°/1.8°(2相又は4相モータ)、1.5°/3° (3相モータ)などがあります。
2、静トルク(保持トルク)について
ステッピングモータの動トルクを確定するのは難しいです。 一般的には、先ずモータの静トルクを決定することにします。 静トルクの選択は、モータが作動する負荷に基づき、負荷は慣性負荷と摩擦負荷の2種類に分けられています。 単一慣性負荷及び単一摩擦負荷は存在しません。 直接(通常は低速で)起動する時、二種とも考える必要があります。 加速起動する時、主に慣性負荷を考えてください。 定速作動する時、摩擦荷重のみを考えてください。 通常の場合、静トルクは摩擦負荷の2ー3倍以内にすべきです。 静トルクが選定されたら、モータのベースと長さ(幾何学的サイズ)を決定することができます。
3、電流について
静トルクのモータは、電流パラメータが違うため、作動の特性もかなり違います。 モータの電流は、モーメント周波数特性曲線(基準駆動と駆動電圧)に基づいて判断することができます。
4、トルクとパワー
ステッパーモーターは一般的に広範囲で速度が変化しながら使用され、出力も変化し続けます。 一般に、トルクのみによって測定されます。 トルクと出力は次のように変換されます。
P=2πnM/60
P= Ω·M
Ω=2π·n/60
Pはパワー、単位はワット。Ωは毎秒の角速度、単位はラジアン。nは毎分の回転数、Mはトルクの単位(ニュートン・メートル)。
P=2πfM/400(ハーフステップ)
fは1秒当たりのパルス数(PPSと呼ぶ)
(二)、使用中の注意事項
1、ステッピングモーター低速の場合、1分間の回転数は1000 rpmを超えず(0.966°6666PPS)、1000-3000PPS(0.9°)はベストで、減速装置を通して作動することが可能です。この時点でモーターの作業効率は高くて、低騒音です。
2、ステッピングモータ全体の手順を使用しない方が良いです。全体のステップ状態にすると、振動が大きいです。
3、歴史的な理由のため、12V電圧のモータのみが12Vを使用できます。他のモーターの電圧値は駆動電圧ボルト値ではありません。駆動電圧は、ステッピングモータドライバーにより選択できます。もちろん、12V電圧のモータは12V定電圧駆動以外、他の駆動電源を使用することもできます。ですが、温度上昇問題を注意しなければなりません。
4、大きな慣性負荷は、大きいフレームサイズのモータを選択する必要があります。
5、高速または高慣性負荷モーター、一般は働いていない速度でスタートし、徐々にスピードアップします。こうしたことで、モーターが出てない、同時に騒音を減らすことができます。また、停止の位置決め精度を向上することもできます。
6、高精度必要の時、機械的減速を介して、モータ速度を向上し、又はドライブの高分画の使用によって解決します。5相モータを使用することもできますが、システム全体の値段がより高くなり、生産するメーカもあまりないです。
7、モーターは振動領域で駆動しない方が良いですが、もしどうしても駆動するなら、電圧、電流を変更したり、ダンピングを加えたりするによって、解決できます。
8、モータは600PPS(0.9°)以下で作動し、小電流、大きなインダクタンス、及び低電圧で駆動する必要があります。
9、モーターを先に選択し、それからドライバを選択する原則をしっかり守ってください。
記事のソース:https://www.skysmotor.com/goods-50-Nema-17-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF-59Ncm-84ozin-2A-42x48mm-4-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC-w-1m-Cable-Connector.html

